ウィンナ・シュランメルン その6
8.落穂は拾えるか
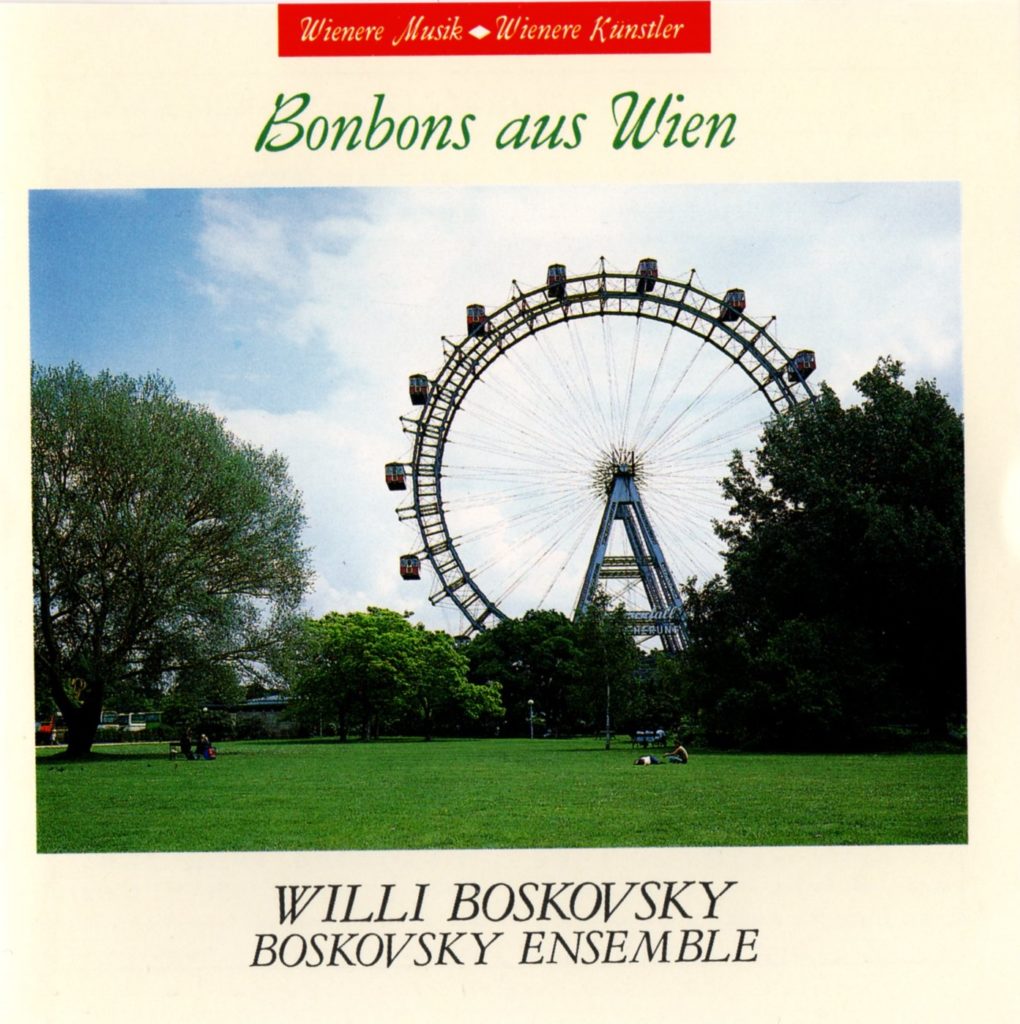
先日ふと思いついて、ボスコフスキーのヴァンガード録音『ウィーンのボンボン』と『ウィーンのロリポップ』、『ウィーンのクリームパイ』を購入した。1950年代後半の彼が主宰する合奏団のもので、私はモーツァルトの行進曲や舞曲のものだけを集めたCDを持っているが、ワルツ等のものはこれまで無視していた。何という能天気なタイトルだろうとは思いつつも、ひょっとしてシュランメルン・スタイルのものもあるのでは、と思った次第である。解説書には、編成や奏者名が記されておらず、耳で確かめるしかないが、ワルツ全曲とレンドラ―1曲、計10曲がシュランメル・スタイルでの演奏である。
ボスコフスキーは実に気持ちよさそうに演奏している。しかし、残念ながらシュランメル・スタイルとしては出来は悪いと思う。タイトルを能天気だと思った通りの演奏である。
シュランメルン・スタイルというのは、ジャズのコンボで言えばワンホーンのカルテットであり、そこで最も大切なのがホーンとリズム・セクションとのインタープレイである。ワンホーン・カルテットで成功するのは非常に難しいと言われるが、それはこのインタープレイのまずさが、直ちに聴くものの耳に届いてしまうからである。ボスコフスキーの演奏の欠点は、あまりできの良くないワンホーン・カルテットと同じである。おそらく優秀なリズム・セクション・メンバーなのだろうが、ここには両者のインタープレイが弱い。したがって弾性がない。録音あるいはミキシングが、シュランメルン・スタイルには向かない、オーケストラの響きを意識したものであることがそれをさらに際立たせている。
このボスコフスキーのものは1958年の録音とのこと、第2回の稿でウィーン・フィルのメンバーによる録音の最初のものが1982年と書いたのは間違いであり、ボスコフスキーの初録音はヴァンガードとともに、その功績は評価しなければならないと思う。
本題の落穂拾いに入ろう。
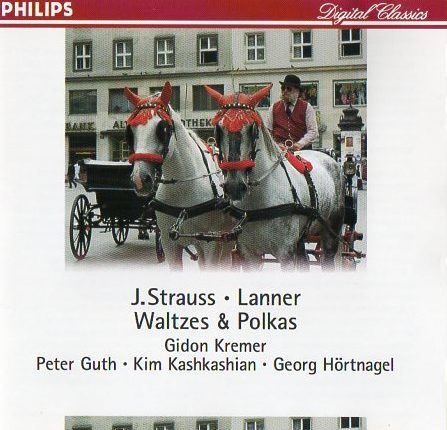
クレーメルがビオラのカシュカシアンなどの仲間とともに録音したのが、「J.シュトラウスとランナーのワルツとポルカ集」というシュランメルン・スタイルでの演奏である。日本で発売されたのはずっと後だったと思うがこれは1982年の録音で、先駆的なものと位置付けられるだろう。やはり80年代冒頭あたりだと「古きウィーン」というのは、このクレーメルのバイオリン的なものと捉えられていたのだろうか。現代的なスタイルのヴァイオリニストであるクレーメルとは思えない、ポルタメントを多用したメロメロの奏法である。リズム・セクションはお付き合い程度のもの、クレーメルの独り舞台、したがって失敗作である。

/ワルツ・ポルカ集
92年にアルバン・ベルク弦楽四重奏団にコントラバスが加わるという五重奏のものが5曲録音されている。評判のいいCDであったが、私は嫌いである。編曲もあるのだろうが、弦楽四重奏的に密度の高い内声部が、シュランメルン・スタイルの弾力を削ぐ形になっている。さらに、ウィーン音楽特有のリズムに加え、弦楽四重奏特有と言っていいのだろうか、もうひとつ別の「波動」がかぶさっている。私はこれが気持ち悪い。
同じCDの後半は、シェーンベルクなど新ウィーン学派の作曲家による、編曲ものが数曲収録されている。彼等の編曲は時折取り上げられることがあり、前述のビーダーマイヤー・ゾリステンにも録音がある。正直、何の必要があってこのような編曲がなされているのか、私は理解できない。耳障りなだけである。
ヴァイオリン2丁、ビオラ、コントラバス編成のものは以上である。落穂拾いの範囲をもう少し広げて、ヴァイオリン2丁、カウンター(コントラ)ギター、G管クラリネット、アコーディオンの編成のものも見てみたい。このスタイルがシュランメルの始めたものに一番近いのかも知れない。楽しくはあるが、少々ホイリゲ風に傾くところがあるようだ。かつてよく民族音楽的に扱われていたため、あまり真剣に聴いたことがなかったが、近年はこのスタイルの演奏の方が主流になっているかも知れない。多くの演奏があるが、ここでは次の3つを取り上げるにとどめる。

初めてこのスタイルで聴いたのは、マロート・シュランメルンの『ウィーンかたぎ/シュランメルに乾杯!』という1987年、CBSソニーによって日本で録音されたものである。「シュランメルに乾杯」は日本盤の表題であるが、シュランメルのものは2曲だけである。ソプラノによるウィーン歌曲も数曲入っている。私の愛聴してきた、大好きなCDである。
リーダーはアコーディオンのマラート、写真を見る限りこの人は身長2メートルほどの大男である。アコーディオンも小さく見える。第1ヴァイオリンはウィーン・フィル出身のラリシュ「教授」とのことだ。恐ろしく古いスタイルの演奏である。ルバート、ポルタメント、何でもありだ。「教授」のヴァイオリンは時々音程をはずす。全員揃って音程の「ずり下がり」が起こることもあるが、これは意図的か? 聴きなれてくると、これがまた楽しいのである。
このCDにはマルガリータ・トゥシェックの歌う数曲のウィンナ・リートが入っているが、これがなかなか楽しい。「ウィーン、わが夢のまち」など、シュワルツコップなどの「上手」な歌手や、その他多くのウィーン・リート歌手たちも歌っているが、このおばさんの歌うものが、はるかにウィーンらしい情緒があるように思える。
私が拾いたい落穂はこの一枚だけかも知れない。

97年にウィーン・シュランメルン・アンサンブルの『ランナー:四季』が録音されている。G管クラリネットに替えてフルートであるが、全体的に響きが軽く、これはビールでも飲みながら、BGMとして鳴っているといいと感じる音楽である。ツィラーやコムツァークⅡ世など、あまり聴くことのない作曲者のものが主体になっており、少々薄っぺらい音楽に感じる。これはもうビーダーマイヤー・アンサンブルなどのシュランメルン・スタイルの演奏などとは、本質的に別のものである。残っているのは、このような「ニッチ」なものになってしまったのだろう。

2004年にグラモフォンによって録音されたのが、ウィーン・フィルの名手たちで編成されたウィーン・フィルハーモニア・シュランメルンのWeiner Typen『これぞウィーン』である。マロート・シュランメルンと同編成であるが、音楽の味わいは全く異なっている。これは危ない演奏である。G管クラリネットが暴れまわり、頭が空っぽどころか、破裂してしまいそうである。これは間違いなく聴く人の頭を悪くする。
CDタイトルの行進曲「これぞウィーン」はG管クラリネットが入っていない曲で、これなど、さすがウィーン・フィルの名手たちの演奏だと感心させられる。どうしてこんなにG管をフィーチャーするのだろうと不思議に感じる。一度聴いたら、しばらく聴きたくなることはなさそうである。
ここあたりで、私のウィンナ・シュランメルンお遍路さんはおしまいである。わかったことはただ一つ、世の中には完璧ということもあるのだ、ということである。ビーダーマイヤー・アンサンブル・ウィーンの残した完璧な作品、あれで終わりだったのだ。

