『ある微笑』のモーツァルト~不協和音四重奏曲(1)
サガンのことは良く知らないが、昔読んだ『ある微笑』は不思議に心に「引っかかった」小説である。あらすじを訳者朝吹登水子氏の解説から引用させていただく。
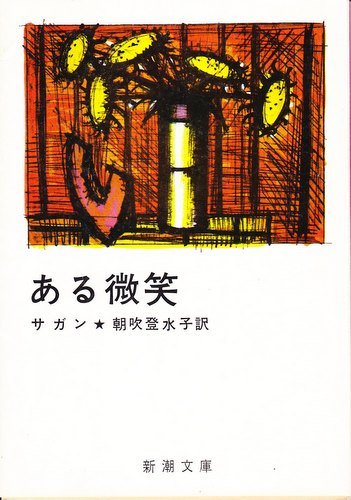
「“ある微笑”は、ドミニックという少女の恋物語である。人生に倦怠している二十の娘、かの女には、ベルトランという、ソルボンヌ大学の級友の情人〔アマン〕がいる。かの女は、ある日、ベルトランの叔父である、四十男の、憂鬱で、孤独なリュックという男に逢って、強く惹かれる。リュックはドミニックに、後腐れのない、一時的な恋愛遊戯をしようと申し込む。かの女はこの遊びに危険を感じるが、結局受諾する。二人は、南仏のカンヌで楽しい二週間を過す。しかし、ドミニックは、この男を真に愛するようになって了う。やがて、夏休みも終り、二人は巴里に帰って各自の生活に戻る。リュックは妻の許に、ドミニックはソルボンヌ大学へ……。ドミニックは、この堪えがたい心の傷に打ち勝とうと、灰色の巴里の窓の空の下の、孤独な一室で、じっと堪え、苦しむ。」そして……。
以下、本文の末尾を引こう。
十五日め、私は気前の良い隣人が大きな音でかけているラジオの音楽に目を覚まされた。それはモツアルトの美しいアンダンテで、いつものように、暁と、死と、ある種の微笑〔ほほえみ〕とを私に呼び起させた。私はじっとしたまま、お床の中で長いことそれに耳を傾けていた。私は割に幸福だった。
下宿の女主人が私を呼んだ。誰かが電話をかけて来たのだ。私はゆっくりと部屋着を引っかけると、階下に降りて行った。私はリュックだと思い、そして今ではもうさほど重大なことではなくなったと思った。何かが私から逃げていったのだ。
「君、元気?」
私はかれの声に聞き入った。それはかれの声だった。この平静さ、この優しさは一体何処から私にやって来たのだろう。かれは私に翌日お茶を飲もうと言った。私は『ええ、ええ』と言っていた。
私は非常に用心深く部屋に戻って行った。音楽は終っていた。そして私は終りを聴き損ねたことを残念に思った。私は不意に鏡の中の自分を眺めた。私は自分がほほえんでいるのを見つけた。私はほほえむことをやめることが出来なかった。私には出来なかった。再び、私は知っていたのだ、自分が独りだということを、私にはこの言葉を自分自身に言って見たかった。独り、独り、だけどもそれが一体なんだ? 私は一人の男を愛した一人の女だった、それは単純な物語だった。鹿爪面をすることもないのだ。
ドミニックの「自己」は複雑である。小説にあらわれるのは、本来の自分である「自意識の自分」、外との接触時に演じられる「ペルソナとしての自分」、それに「自分を見つめている自分」である。さらに記述の主体である、それらの自分を「俯瞰している自分」、第四の自己である。「自意識としての自分」は「ペルソナとしての自分」を嫌悪し、「自分を見つめている自分」は「自意識としての自分」を侮蔑する。そして「俯瞰している自分」はすべてをシニカルに見、そして文章にする。こういう構造の中では「自意識としての自分」の中には倦怠しか無くなってしまうだろう。ドミニックの心の動きを理解することは容易ではない。
しかしながら、ドミニックの「ペルソナとしての自分」はリュックへの愛と挫折、妻フランソワーズの善良さによって消え去ってしまう。そして最後に平静さと優しさの中で「ええ、ええ」と答えることができたのだ。そう答えることのできた「自意識としての自分」と「自分を見つめている自分」は、鏡の中でほほえんでいる自分の姿を通して和解する。「独り、独り、だけどもそれが一体なんだ? 私は一人の男を愛した一人の女だった、それは単純な物語だった。鹿爪面をすることもないのだ。」この最後の「俯瞰している自分」自身が発する言葉、ここにはすでにシニカルさはない。『ある微笑』は「単純な“自己回復”の物語」だったのである。この自己回復を通して、ドミニックは一人の少女から一人の女へと変貌するのだ、確固たる「独り」に支えられて。
私の関心は、この自己回復のメタファーとして使われている「モツアルトの美しいアンダンテ」とは一体どの曲のものか、ということである。本文で若いカップルと中年夫婦の「四重奏〔カルテット〕」という言い方がなされているように、それは弦楽四重奏曲であることに間違いはない。そしてその「聴き損ねた終わりの部分」、これこそが決定的に重要なのである。「ある微笑」である。第1ヴァイオリンはドミニック、チェロはリュック、これは確実だろう。そして最も善人だが最終的な支配力を持っているフランソワーズはビオラ、存在感の薄いベルトランは申し訳ないが第2ヴァイオリンである。
私は、この曲は弦楽四重奏曲第19番ハ長調『不協和音』K.465の第2楽章アンダンテ・カンタービレ、そして「微笑」はそのコーダ以外にあり得ないと思っている。
この楽章は、展開部を省略したソナタ形式であるが、かなり変則的である。詳しくは次回にまわすことにして、ここでは『ある微笑』での「四重奏仕立て」に擬えて聴いてみよう。もちろんこんな聴き方は邪道であるが、アマチュアだけに許される遊び、とご容赦いただきたい。

提示部は3つの主題を持っている。最初の主題は言われているほど「美しい」だけのものではない。内に鬱が籠っている。2番目の主題では、チェロの呼びかけに呼応する形で、第1ヴァイオリンがともに歌う。しかしそれは絶え絶えで歌声にはならず、神秘的な響きのうちに3番目の主題へと入る。チェロが執拗に引きずり込むような音型で呪縛する。他の楽器はその上で飛翔しようとするが、その執拗な呪縛を逃れることが出来ない。再現部では、3番目の主題はさらに執拗に2回反復されるのだ。コデッタのほの明るさの中で何が起こったのだろうか、突然、コーダで第1ヴァイオリンは独り高く飛翔する。何という旋律だろう。チェロはもう呪縛をすることはできず、第2ヴァイオリンも共に歌おうとするが、第1ヴァイオリンはさらに高く飛翔をつづける。このコーダこそ「ある微笑」、天上のほほえみである。最後にチェロは1小節の呪縛のモチーフを奏でるが、地上に引き戻すことはもうできない。

